『だいくとおにろく』の教え
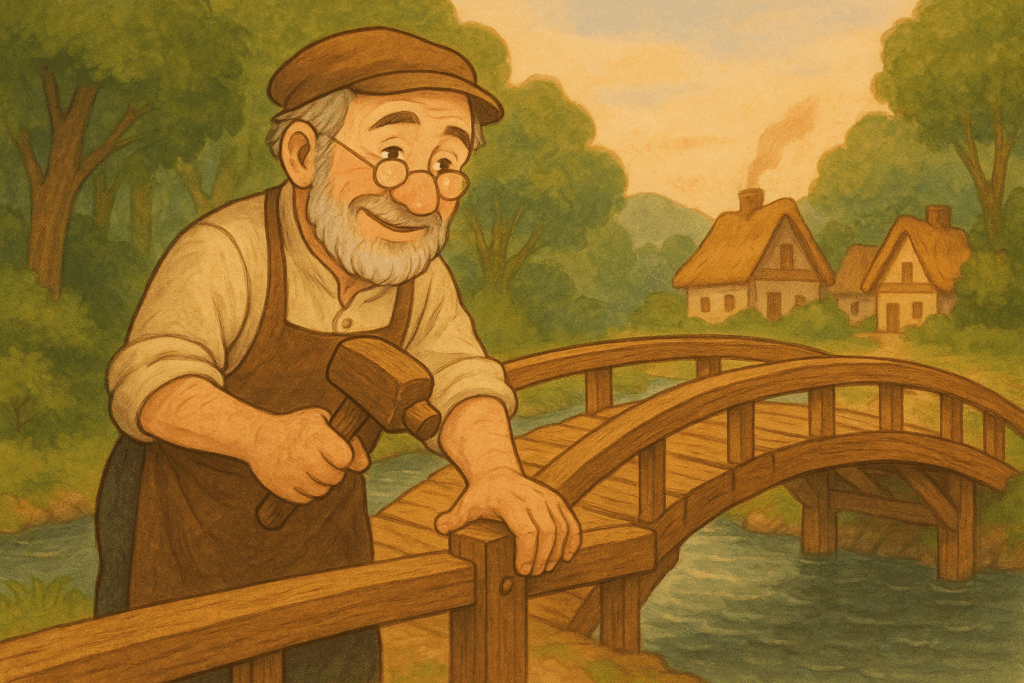
昔話『だいくとおにろく』をご存じでしょうか。
氾濫のたびに橋が壊れてしまう、そんな激しい川の流れに人々は長年困り果てていました。
腕の立つ大工に頼んでも、どうしても橋を架けることはできません。
ある日、大工の前に鬼が現れます。
鬼は見事な橋を作り上げますが、代わりに大工の目玉を要求します。
ただし、大工が鬼の名前を当てることができれば、目玉は取らないと言います。
必死に鬼の名前を探し続けた大工は、ついにその名を言い当て、鬼は力を失って消えていきます。
この「名前を当てる」という行為は、単なる物語の面白さにとどまらず、人間の心理の深い部分とつながっています。
心理学の世界では、感情や状態を言語化し、名前を与えることで人はそれを客体化できるといわれています。
さらに、六という数字は古来、完全に届かない不安定さを象徴することもあり、物語の鬼の名前「おにろく」にもその意味が重なります。
名前がないうちは、恐れや混乱は正体の見えない「鬼」のようなもの。
しかし、言葉にして名を与えた瞬間、それは輪郭を持ち、向き合える相手になるのです。
外国につながる子どもたちの心
外国につながる子どもたち――つまり、家庭に異文化のルーツを持ち、日本社会の中で複数の文化のはざまで育つ子どもたちは、しばしば複雑な感情を抱えています。
たとえば、学校で友達とうまくなじめない、家では自分の文化や言語が十分に受け入れられない、周囲からの偏見や無理解に傷つく――そうした体験は、子どもたちの心に「なんだかわからないけれど重たい気持ち」を残します。
さらに、
日本語の体験を英語や母国語で親に伝える難しさ
逆に英語や母国語での体験を日本語で友達に伝える難しさ
生活言語と学習言語の違い
口頭説明だけではわかりにくい遊びや生活のルール
こうしたことが積み重なると、仲間に入れなかったり、入れてもらえなかったりすることがあります。
ときには、からかわれて嫌な思いをすることもあるでしょう。
このとき、子どもたちは「これは悲しみ?怒り?それとも寂しさ?」と、自分の感情を整理するための言葉を持てないことが少なくありません。
なぜなら、異文化体験の中では、親もまた言葉を見つけられず、家庭の中で感情をゆっくり分かち合う余裕がないことが多いからです。
その結果、文化や言語の壁を前に、説明しようという気力を失ったり、「もう面倒くさい」と感じて伝えることを諦めてしまったりするかもしれません。
ときには、親が先回りして「これはこういうことなのよ」と決めつけ、子どもが自分なりに言語化しようとする機会を奪ってしまうこともあります。
こうして、子どもは心の中で、正体の見えない「鬼」を抱え込むことになるのです。
心理学理論からのアプローチ
ここで役立つのが、心理学者ダニエル・シーゲル(Daniel Siegel)が提唱した「ネーム・イット・トゥ・テイム・イット(Name it to tame it)」という考え方です。
これは、感情や体験に名前をつけることで、それを飼いならし、整理し、心を落ち着かせることができる、というものです。
脳科学の研究でも、感情をラベル付けすることで扁桃体の過剰な活動が抑えられ、前頭前野が活性化し、冷静さを取り戻せることが示されています(Lieberman et al., 2007)。
つまり、支援者が子どもと一緒に「これは怒りだね」「これは寂しいんだね」と共感的な言葉をかけるだけで、子どもの心は少しずつ安心を取り戻していけるのです。
さらに、異文化適応理論で知られるジョン・W・ベリー(John W. Berry)が提唱した「文化適応ストレス(acculturative stress)」の概念を用いると、子どもたちが何に苦しんでいるのか、どの部分に名前を見つけてあげるべきかが見えてきます。
文化の違いや期待の不一致、差別的な経験など、日常の中の具体的な葛藤を言語化することで、子どもは次第に「これは私のせいじゃない」「これは私の問題ではなく、環境や周囲の問題なんだ」と距離を取り、自分を守れるようになります。
そうすることで、子どもは少しずつ自己肯定感を取り戻し、自分を過剰に責めなくなり、今の状況を冷静に把握できるようになっていくのです。
名前に気づくことは力を取り戻すこと
心理支援の場で最も大切なのは、問題を過度に分析することではありません。
まずは、子どもの心に湧き上がる感情や体験に、そっと「名前に気づく」ことです。
それは、昔話『大工とおにろく』を思わせます。大工が鬼の名前に気づき、それを言い当てたとき、鬼は力を失い、消えていきました。
名前がわかるということは、見えなかったものに輪郭が与えられ、対話できる相手になるということです。
子どもの心の中に潜む見えない鬼――「寂しさ」「怒り」「不安」。
私たち支援者や大人が「これは寂しさだね」「これは怒りなんだね」と、そっと名前に気づき、寄り添い、伝えることで、その感情は子どもを支配する力を失い、静かに対話できるものへと変わっていきます。
異文化の中を生きる子どもたちは、時に言葉を失い、孤独に沈み込むことがあります。
だからこそ私たちは、時間を共に過ごし、体験を共有し、言葉を紡ぐ支援をするのです。
「名前に気づく」という優しく慎ましい営みを通して、子どもは自分の心を理解し、恐れに立ち向かう力を取り戻していきます。
それはきっと、子どもたちにとって長く心に残る、かけがえのない心理的な贈り物になるでしょう。
📚 参考文献
- Daniel J. Siegel (2010). The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind. Delacorte Press.
- Lieberman, M.D., et al. (2007). “Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli.” Psychological Science, 18(5), 421–428.
- John W. Berry (1997). “Immigration, Acculturation, and Adaptation.” Applied Psychology, 46(1), 5–34.
- 松居直著・赤羽末吉イラスト, だいくとおにろく, 福音館書店, 1967

コメントを残す