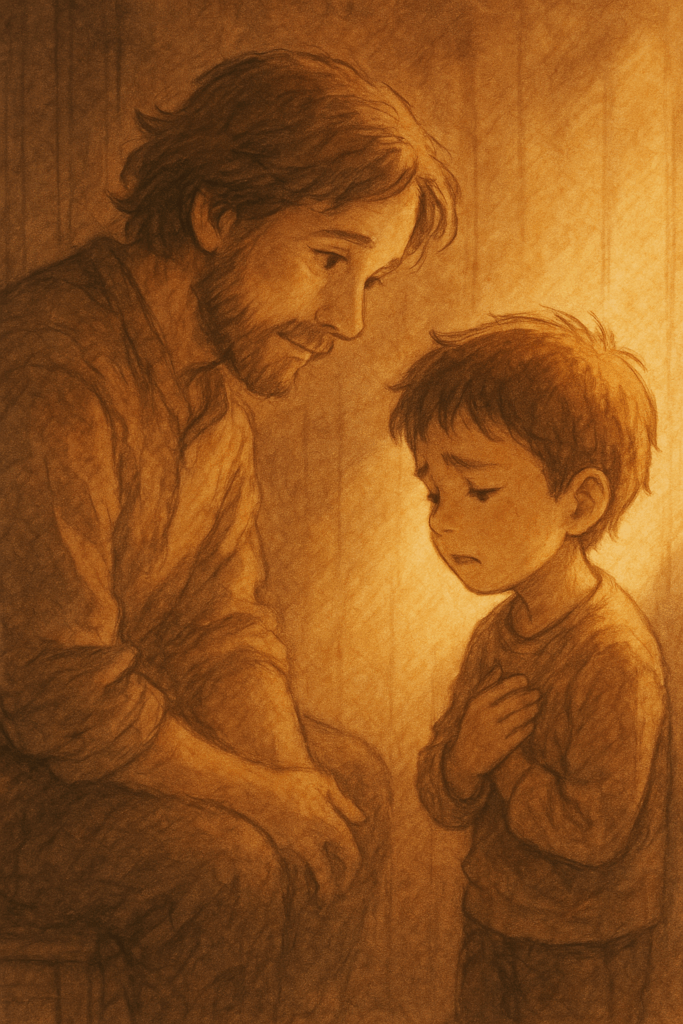
「上手だね」と言えないときの戸惑い
子どもがたどたどしく音読したり、漢字のバランスが不安定だったりすると、「まだ上手とは言えない」と感じてしまうことがあります。
無理に「よくできたね」と褒めようとすると、どこか白々しく感じたり、嘘をついているような違和感に戸惑うこともあります。
しかし、その感情は、誠実に子どもと向き合おうとする親の願いの表れです。
沈黙期とは?──話さないのではなく、育っている時間
とくに「外国につながる子ども」や第二言語を学ぶ子どもには、言葉がうまく出ない「沈黙期」があります(Krashen, 1985)。
この時期、この瞬間というのは、話さない時期ではなく、言語を内側で吸収し、理解を深めている大切な時間なのです。
不安や恥じらい、自信のなさなどが、言葉ではなく沈黙として現れているのです。
褒めることは、評価ではなく“共感”
この時期に大切なのは、結果を評価するのではなく、子どもが何を感じ、どう取り組もうとしているかを受け止めるまなざしです。
心理学者カール・ロジャーズが述べた「共感的理解」は、相手の内的世界に寄り添う姿勢であり、「上手だね」という評価ではありませんでした。
「ちょっと緊張してたけど、一生懸命読もうとしてたね」「この漢字のこの線は、カッコよく書けてたね」といった気持ちへの共感が、子どもに安心感を与えます。
「褒めたら成長しない?」という誤解
「ここで褒めたら満足して成長しないのでは?」という疑問がわくこともあります。
しかし、内発的動機づけ理論(Deci & Ryan, 1985)によれば、人は外からの評価ではなく、自分なりの意味づけによって行動を続けようとします。
ヴィゴツキー(Vygotsky, 1934)は、学びは他者との関係の中で育つと説きました。
沈黙期の子どもにとって、安心できる他者の存在が、やがて言葉を取り戻すきっかけになります。
「あなたのがんばりを見ているよ」というまなざしこそが、心理的安全性となり、子どもの挑戦を支える力になるのです。
終わりに──「できる・できない」を超えて見つめる力
子どもの沈黙の中には、見えない努力があります。「おとうさん、みて」「できたよ」と言っていた頃のように、誰かに見てほしい、伝えたいという思いが、今も静かに息づいているのです。
だからこそ、焦らず「ことばになる前のがんばり」に光をあて、「できる・できない」ではなく、「やろうとしていた姿勢」に目を向けることが大切です。
「今は話せなくても、わからなくても、それでも信じているよ」──そのまなざしが、沈黙の中にある子どもにとって、何よりも温かく力づよい“ことば”になるのです。
本当に大切なのは、今できなくても信じること。
将来できるようになるはずと期待するのでもなく、たとえこの先できるようにならなかったとしても、それでもあなたを信じているという姿勢です。
では、何を信じるのでしょうか?
それは、子どもの“成果”や“能力”ではなく、今、この子が、わからないながらも、言葉にならないがんばりを続けていること、
焦って目に見える結果を求めすぎず、「できる・できない」という尺度を手放して、その子なりの「やってみようとした気持ち」や「やろうとした姿勢」に目を向けるまなざし、
たとえ言葉にならなくても、子どもはその時、その時を精一杯生きています。
だからこそ、結果ではなく、その瞬間、瞬間を信じること。
その時、その時の気持ちを信じること。
それが、沈黙期の子どもにとって、最もあたたかな「応援の思い出」になるのだと思います。

コメントを残す